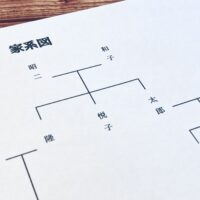お役立ちコラム
5.42025
ご両親の想いを未来へ繋ぐ-夫婦相互遺言の作成

こんにちは!行政書士なかじま法務事務所の中島英貴です。
今回は、先日サポートさせていただいた「夫婦相互遺言」の公正証書作成について、ご紹介させていただきます。ご両親の将来を案じ、早めに相続対策を進めたいとお考えの方の参考になれば幸いです。
きっかけは、息子さんの心配から
3月中旬、40代の男性(息子さん)から、「父に遺言書を作成してもらいたい」というご相談をいただきました。お話を伺うと、最近お父様が少し物忘れが多くなられたとのことで、今のうちにしっかりとご自身の意思で遺言を作成しておきたい、と息子さんがお考えになったのがきっかけでした。
息子さんは、すでにお父様が自筆で書かれたという遺言書を2通、大切にお持ちでした。1通は「全財産を妻(お母様)に相続させる」という内容、もう1通は「妻(お母様)が先に亡くなった場合は、全財産を息子(ご相談者様)に相続させる」という内容でした。
自筆証書遺言の「落とし穴」と公正証書のご提案
お父様がご家族を想って遺言書を準備されていたお気持ちは、大変素晴らしいものです。しかし、この2通の遺言書には、見過ごせない問題点がありました。それは、2通とも同じ日付で作成されていたことです。
同じ日付の遺言書が複数存在する場合、どちらの内容を優先させるべきか判断が難しく、かえって相続トラブルの原因となってしまう可能性があります。
そこで、私から以下の提案をさせていただきました。
- 1通の遺言書にまとめる: 現在の内容を維持しつつ、まずはお母様へ相続させ、もしお母様がお父様より先に亡くなられた場合(または同時に亡くなられた場合)には、息子さんへ相続させる、という内容を「予備的遺言」として1通の遺言書に盛り込むこと。
- 「公正証書遺言」で作成する: 公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがなく、法的に最も確実で安全な方法であること。
ご両親との面談、そして「夫婦で一緒に」という決断
1週間後、息子さんと一緒にご実家を訪問し、お父様、お母様と直接お会いしました。お父様にお話を伺うと、ご自身の財産をご家族に残したいという明確な意思をお持ちでした。
一方、お母様は意識もはっきりされており、当初は「自分は自分で書くから大丈夫(自筆証書遺言)」とおっしゃっていました。
そこで、念のため私から改めて遺言についてご説明させていただきました。
- なぜ遺言が必要なのか(相続手続きの円滑化、トラブル防止)
- 遺言の種類(公正証書遺言と自筆証書遺言)とそれぞれのメリット・デメリット
- ご夫婦がお互いに遺言を遺す「夫婦相互遺言」の意義
- 万が一に備える「予備的遺言」の重要性
私の説明を熱心に聞いてくださったお母様は、「それなら、私も主人と一緒に公正証書で作ってもらいたい」と考えを変えてくださいました。ご夫婦で同じタイミングで、同じ方法で遺言を作成されることは、後々の手続きを考えても非常にスムーズです。
この日は、今後の手続きに必要な委任状(戸籍謄本や不動産評価証明書などの取得のため)にご署名をいただき、帰路につきました。
面倒な書類収集は専門家にお任せ!
3月末、委任状に基づき、区役所と都税事務所で必要書類の収集を行いました。年度末という時期もあり、窓口は大変混雑していました。戸籍謄本、住民票、不動産評価証明書など、遺言作成に必要な書類は多岐にわたります。これらを多忙な息子さんがご自身で平日に休みを取って収集するのは、時間的にも大きな負担だったはずです。専門家にご依頼いただくことで、こうした手間や時間を節約できるのも大きなメリットの一つです。
案文作成から公証役場との連携までスムーズに
必要書類が揃い、いよいよ遺言書の案文作成に取り掛かります。今回は、相続財産の内容が比較的シンプルで、相続人もご家族(お父様、お母様、長男様、次男様)に限られていたため、遺言の案文もスムーズに作成できました。
すぐに、日頃から連携させていただいている公証役場の公証人の先生に連絡を取り、4月末に作成日の予約を入れました。同時に、収集した書類と私が作成した遺言の案文をお送りし、内容を確認していただきます。幸い、案文はほとんど修正なく、ほぼそのままの内容で進められることになりました。
証人もお任せください
公正証書遺言の作成には、信頼できる証人2名の立会いが必要です。今回は、証人の一人を私自身が務め、もう一人は行政書士会の活動でお世話になっている先輩行政書士にお願いしました。ご家族や相続に関係する方は証人になれませんが、行政書士にご依頼いただければ、守秘義務のある信頼できる証人をご用意できますので、ご安心ください。
作成日までの間、息子さんには時折進捗状況をご連絡し、何か不明な点があればいつでも遠慮なく質問していただけるようお伝えしました。
いよいよ作成当日、そして安堵の瞬間
作成日当日。待ち合わせの時間に、息子さんがお父様とお母様を連れて公証役場に来られました。
まずはお父様が、私ともう一人の証人と共に公証人の先生の待つ部屋へ。公証人の先生が、いくつか簡単な質問をされ、お父様の意思能力(遺言の内容を理解し、判断できる能力)と、遺言を作成する意思を最終確認します。ご高齢の方や、少し物忘れが見られる方の場合でも、遺言を作成する瞬間にご自身の財産を誰に遺したいか、その内容をきちんと理解・判断できる状態であれば、遺言は有効に作成できます。
公正証書遺言では、法律の専門家である公証人が、その点をしっかりと確認した上で作成を進めるため、後々のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。ご高齢ということもあり、少しドキドキしましたが、公証人の先生の巧みな質問のおかげで、無事に確認が取れました。
その後、公証人の先生が遺言書の内容を読み上げ、内容に間違いがないことを確認した後、お父様、私、もう一人の証人がそれぞれ署名・捺印し、お父様の公正証書遺言は無事に完成しました。
続いて、お母様も同様の流れで、滞りなく公正証書遺言を作成することができました。
一連の手続きが完了したとき、一番ほっとした表情をされていたのは、息子さんだったかもしれません。ご両親の想いをしっかりと法的な形で残すことができ、将来への安心を得られた瞬間だったと思います。
まとめ:早めの準備と専門家への相談が「安心」の鍵
今回の事例を通して、改めて以下の点を強く感じました。
- 認知症への備え: 判断能力が低下する前に遺言を作成しておくことの重要性。
- 遺言の形式: 自筆証書遺言も有効ですが、要件不備や紛失、解釈をめぐるトラブルのリスクを考えると、公正証書遺言が最も確実で安心です。
- 夫婦相互遺言・予備的遺言の活用: ご夫婦で遺言を準備し、万が一のケースにも備えることで、より円満な相続につながります。
- 専門家の活用: 相続や遺言は、法律や手続きが複雑に絡み合います。行政書士にご相談いただければ、書類収集の代行から、最適な遺言内容のご提案、公証役場との連携、証人の手配まで、トータルでサポートいたします。何より、ご本人様やご家族の精神的な負担を軽減することができます。
ご自身の、またはご両親の終活や相続について、少しでも気になること、ご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。お客様一人ひとりの状況に合わせ、最適な解決策をご提案させていただきます。
東京都台東区で「お困りごとを解決する」行政書士をしております。
遺言・相続・医療法人設立・建設業許可・会社設立などのご相談を承っております!