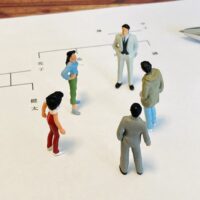お役立ちコラム
9.202024
遺言書作成はなぜ必要?|相続トラブル回避のために

「まだ早い」は間違い? 遺言書作成 の重要性と必要性
「自分にはまだ遺言書なんて早い」「うちは家族仲が良いから大丈夫」そう思っていませんか?しかし、遺言書は、ご自身の人生の集大成として、大切なご家族へ想いを伝え、将来の安心を守るために非常に重要な役割を果たします。
遺言書がない場合の具体的なリスク
もし遺言書がないまま相続が発生すると、法律で定められた相続人(法定相続人)が、法律で定められた割合(法定相続分)で財産を分けることになります。一見公平に見えますが、以下のような問題が起こる可能性があります。
- ご自身の意思が反映されない:
- 長年連れ添った配偶者により多く財産を残したい。
- 家業を継ぐ長男に事業用資産を集中させたい。
- お世話になった特定の人にも財産を分けたい。 このようなご自身の希望は、法定相続分だけでは実現できません。
- 相続人同士の争い(”争続”):
- 不動産など、物理的に分けにくい財産の分割方法で揉める。
- 生前の貢献度(介護など)に対する不満から、法定相続分に納得できない相続人がいる。
- 相続人の間で意見がまとまらず、遺産分割協議が長期化・複雑化する。
- 最悪の場合、家庭裁判所での調停や審判に発展し、家族関係に深い溝ができてしまうケースも少なくありません。
遺言書を作成する5つの大きなメリット
遺言書を作成することで、上記のようなリスクを回避し、多くのメリットを得られます。
- あなたの意思を確実に反映できる: 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるか、ご自身の言葉で明確に指定できます。付言事項として感謝の言葉などを添えることも可能です。
- 面倒な相続手続きがスムーズに進む: 遺言書があれば、原則として遺産分割協議は不要となり、相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約など)が円滑に進みます。相続人の負担を大きく軽減できます。
- 相続人同士の争いを未然に防ぐ: 財産の分け方が明確になるため、相続人間での無用な憶測や対立を防ぎ、円満な相続の実現につながります。
- 特定の人への財産承継が可能に: 法定相続人以外の人(内縁の妻、お世話になった友人、NPO法人など)にも財産を遺贈できます。また、事業承継をスムーズに進めるためにも活用できます。
- 相続税対策につながる可能性も: 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを考慮した遺産分割を指定することで、相続税の負担を軽減できる場合があります。(※税務に関する具体的なアドバイスは税理士の分野となります)
要注意!遺言書作成でよくある5つの間違いと正しい対策
せっかく遺言書を作成しても、形式や内容に不備があると法的に無効になってしまうことがあります。よくある間違いとその対策を知っておきましょう。
- 間違い1:自作遺言書の形式不備で無効に…
- 内容: 日付がない、署名がない、押印がない、全文自筆でない(パソコン作成や代筆)、訂正方法が間違っているなど、自筆証書遺言の厳格な要件を満たしていない。
- 対策: 法律で定められた要件を正確に理解して作成する。不安な場合は、行政書士などの専門家への相談や、より確実な公正証書遺言の作成を検討しましょう。
- 間違い2:証人になれない人を選んでしまう(公正証書・秘密証書の場合)
- 内容: 公正証書遺言や秘密証書遺言の作成には証人2名以上が必要ですが、未成年者、推定相続人(将来相続人になる可能性のある人)、受遺者(遺贈を受ける人)、これらの配偶者や直系血族は証人になれません。
- 対策: 証人の適格要件を確認し、該当しない信頼できる第三者に依頼する。適当な人がいない場合は、行政書士や公証役場で紹介してもらうことも可能です。
- 間違い3:内容が曖昧で遺志が伝わらない
- 内容: 「家は妻に」「預金は子供たちで適当に分けるように」など、どの財産を誰に相続させるのか具体的に特定されていないため、解釈を巡って争いになったり、手続きが進められなかったりする。
- 対策: 不動産は登記簿謄本通りに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで、財産を正確かつ具体的に記載する。行政書士に相談すれば、適切な表現方法のアドバイスを受けられます。
- 間違い4:財産目録の記載漏れ・間違い
- 内容: 遺言書に記載のない財産が見つかったり、財産の内容(特に不動産の表示)が不正確だったりすると、その財産については別途遺産分割協議が必要になったり、遺言執行が困難になったりする。
- 対策: 作成前に財産調査をしっかり行い、正確な財産目録を作成する。財産目録は自筆でなくても良い場合があります(自筆証書遺言の場合、目録はパソコン作成も可だが、各ページに署名押印が必要)。
- 間違い5:保管方法が悪く紛失・改ざんのリスク
- 内容: 自宅の仏壇やタンスに保管していたが、相続発生時に見つからない、他の相続人に隠されたり、破棄・改ざんされたりする。
- 対策: 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する(原本を法務局が保管、検認不要)、公正証書遺言として作成する(原本は公証役場が保管)、信頼できる遺言執行者に預けるなどの方法を検討する。
遺言書作成は専門家(行政書士)への依頼が安心な理由
遺言書の作成は、法律の知識が不可欠な重要な手続きです。「自分でも書けそう」と思っても、後々のトラブルを防ぎ、確実に想いを実現するためには、専門家である行政書士への依頼が安心です。
- 法律に基づいた正確な遺言書を作成できる: 行政書士は相続法規や判例に精通しており、法的に有効で、かつ内容の明確な遺言書を作成するための知識と経験を持っています。形式不備による無効のリスクを避けられます。
- あなたの状況に合わせた最適なアドバイス: ご家族構成、財産状況、ご希望などを丁寧にヒアリングし、自筆証書遺言、公正証書遺言など、最適な遺言の種類や内容をご提案します。
- 相続手続き全体をワンストップでサポート(事務所による): 遺言書の作成だけでなく、相続発生後の遺言執行手続きや、遺産分割協議書の作成、各種名義変更手続きなど、相続に関する手続きを幅広くサポートできる場合があります。(※当事務所の対応範囲はお問い合わせください)
- 他の専門家(弁護士・司法書士・税理士)との連携: 必要に応じて、紛争解決の専門家である弁護士、不動産登記の専門家である司法書士、相続税申告の専門家である税理士と連携し、複雑な案件にも対応します。
遺言書作成を考え始めたら|検討すべき3つのポイント
遺言書作成を決意したら、以下の点を具体的に考えていきましょう。
- どの種類を選ぶ?遺言の種類と比較
- 自筆証書遺言:
- メリット:費用がかからない、いつでも手軽に作成・修正できる。
- デメリット:形式不備で無効になりやすい、紛失・改ざんのリスク、家庭裁判所の検認が必要(法務局保管制度利用時を除く)。
- 公正証書遺言:
- メリット:公証人が作成に関与するため最も確実で無効になりにくい、原本が公証役場に保管されるため安全、検認不要。
- デメリット:費用(公証人手数料)がかかる、証人2名が必要。
- 秘密証書遺言:
- メリット:内容を秘密にしたまま存在を公証できる。
- デメリット:形式不備のリスクは残る、費用がかかる、証人2名が必要、検認が必要。利用されるケースは少ない。 行政書士は、それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、お客様に最適な方式をご提案します。
- 自筆証書遺言:
- 誰に任せる?遺言執行者の選び方
- 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続き(財産の名義変更、引き渡しなど)を行う人です。
- 相続人の代表者や、信頼できる第三者(友人、専門家など)を指定できます。
- 手続きが煩雑な場合や、相続人間での対立が予想される場合は、行政書士などの専門家を遺言執行者に指定することで、スムーズかつ公平な執行が期待できます。
- いつ書くべき?遺言書作成の最適なタイミング
- 遺言書は、判断能力がしっかりしているうち(意思能力があるうち)に作成する必要があります。認知症などが進行すると、有効な遺言書を作成できなくなる可能性があります。
- 「まだ元気だから」ではなく、「元気な今のうちに」作成しておくことが、ご自身とご家族の安心のために重要です。思い立った時が吉日です。
遺言書作成に関するよくある質問(Q&A)
Q: 遺言書は何度でも書き換えられますか? A: はい、何度でも書き換えることができます。新しい日付の有効な遺言書が作成されると、それ以前に作成された遺言書のうち、内容が抵触する部分は効力を失います。
Q: 遺言書は誰かに見せるべきですか?保管はどうする? A: 必ずしも誰かに見せる必要はありません。しかし、相続発生時に遺言書を確実に発見してもらうために、信頼できる人(推定相続人や遺言執行者など)に保管場所を伝えておくか、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用することをおすすめします。
Q: 行政書士に遺言書作成を依頼した場合の費用は? A: 遺言書の種類(自筆証書サポートか公正証書か)、財産の額や種類、内容の複雑さなどによって異なります。当事務所では、事前に明確な費用をご提示いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。公正証書遺言の場合は、別途公証人手数料が必要です。
Q: 認知症になった後でも作成できますか? A: 遺言能力(遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力)があれば作成可能ですが、後々その有効性が争われるリスクがあります。医師の診断書を取得するなど、慎重な対応が必要です。基本的には、判断能力がはっきりしているうちに作成することが重要です。
Q: ペットに財産を残せますか? A: ペットは法律上「物」として扱われるため、直接財産を相続させることはできません。しかし、「負担付遺贈」という形で、信頼できる人にペットの世話を託し、その飼育費用を含めて財産を遺贈する方法があります。
まとめ:元気なうちに遺言書作成で安心な未来を
遺言書の作成は、決して「死」を意識したネガティブなものではなく、ご自身の人生の総仕上げとして、大切な家族への最後のメッセージであり、未来への安心を準備するポジティブな行為です。
「何から始めればいいかわからない」「自分に合った遺言書の書き方は?」など、少しでも疑問や不安があれば、ぜひ一度、相続・遺言の専門家である行政書士にご相談ください。あなたの想いを法的に有効な形で残し、円満な相続を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
【東京都台東区】遺言書作成・相続のご相談は行政書士なかじま法務事務所へ
行政書士なかじま法務事務所は、東京都台東区に拠点を置き、遺言書作成や相続手続きを専門とする行政書士事務所です。
当事務所の強み:
- 豊富な経験と実績: これまで数多くの遺言書作成・相続案件に携わってきた経験に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供します。
- 丁寧なヒアリング: お客様のお気持ちやご希望をじっくりとお伺いし、想いを形にするお手伝いをいたします。
- 初回相談無料: まずは何でもお気軽にご相談いただけるよう、初回のご相談は無料にて承っております。
- 明確な料金体系: ご依頼いただく前に、必ず費用について分かりやすくご説明いたします。
主なサービス内容:
- 各種遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)の作成サポート
- 遺言執行者の就任
- 相続人調査、財産調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続手続き(預貯金解約、不動産名義変更サポート ※司法書士連携)
- その他、相続に関する各種ご相談
「そろそろ遺言書を考えたい」「相続で何をすればいいか分からない」 そんな時は、まずはお気軽に行政書士なかじま法務事務所までお問い合わせください。
東京都台東区で「お困りごとを解決する」行政書士をしております。
遺言・相続・医療法人設立・建設業許可・会社設立などのご相談を承っております!