お役立ちコラム
5.22025
離婚公正証書:顔を合わせたくない元パートナーとの手続き
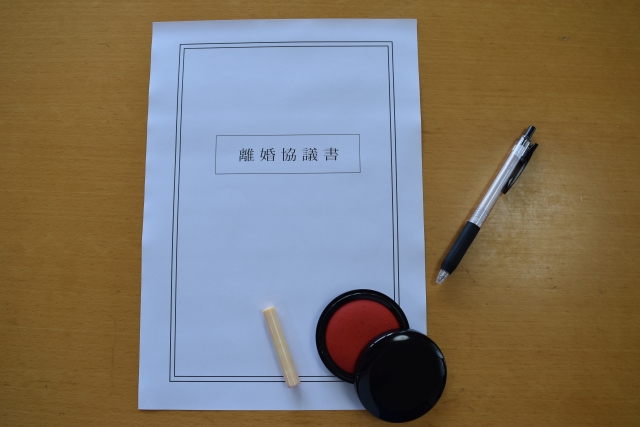
こんにちは!行政書士の中島英貴です。 離婚は、人生における大きな決断の一つ。特に、お子さんがいらっしゃる場合、養育費や面会交流など、将来にわたって決めなければならないことがたくさんあります。
今回は、私が実際にサポートさせていただいた離婚公正証書の作成事例を通して、その重要性と、当事者同士が顔を合わせにくい場合の進め方についてお話ししたいと思います。
「娘が離婚したがっている。協議書を作ってほしい」
昨年秋、そんなご相談を受けました。お話を伺うと、その方の娘さん(40歳)が離婚を決意されたとのこと。10歳になる息子さんがいらっしゃり、親権は娘さんが持ちたい、旦那さんとは性格の不一致が原因で、これ以上詳細を伺うのは控えました。
離婚協議書と公正証書、どっちを選ぶべき?
まず、娘さんと旦那さんとの間で決まった離婚条件をまとめる「離婚協議書」について、通常の書面で作成する場合と、「公正証書」として作成する場合の違い、それぞれのメリット・デメリットをご説明しました。
- 通常の離婚協議書:
- メリット:当事者間で作成でき、費用を抑えられる。
- デメリット:法的な強制力がないため、養育費の不払いなどが起きた場合、改めて裁判などを起こす必要がある。
- 離婚公正証書:
- メリット:公証人が作成に関与し、法的な証明力・執行力が高い。特に金銭(養育費、財産分与など)の支払いについては、不履行の場合、裁判を経ずに強制執行(給与差し押さえなど)が可能になる。
- デメリット:作成に費用と手間(公証役場への出頭など)がかかる。
今回のケースでは、以下の条件で合意ができていました。
- 親権: 娘さん
- 面会交流: 息子さんを大切に思う旦那さんの気持ちを尊重し、制限なく自由に会えるようにする。
- 財産分与: 夫婦共有名義の不動産を売却し、その代金を半分ずつ分ける。
- 養育費: 息子さんが大学を卒業するまで、毎月取り決めた額を口座に振り込む。
特に養育費は、息子さんが成人するまで続く長期的な約束です。「万が一、支払いが滞ったら…」という不安を解消するため、強制執行力のある公正証書で作成することを強くお勧めし、その方向で進めることになりました。
「できるだけ元夫とは顔を合わせたくない…」代理人制度の活用
公正証書を作成するには、原則としてご夫婦そろって公証役場に出向く必要があります。しかし、娘さんからは「できるだけ旦那さんとは顔を合わせたくない」という強いご意向がありました。
このような場合、「代理人」を立てることで、本人が公証役場に行かなくても手続きを進めることが可能です。今回は、私が旦那さんの代理人を務めることになりました。
離婚当事者の代理人として公正証書を作成するには、単なる委任状だけでは不十分です。公証役場が定めた形式に従い、事前に作成した離婚協議書の案文(離婚の条件を具体的に記載したもの)と委任状を合綴(一つに綴じ合わせること)し、そこに旦那さんご本人の実印での捺印と印鑑証明書が必要になります。
私は、お二人の間で合意された内容に基づき案文を作成し、いつもお世話になっている公証役場の先生に内容を確認していただきました。事前にしっかりと準備を整えることが、スムーズな手続きの鍵となります。
緊張の当日、そして未来への一歩
証書作成当日。私は旦那さんの代理人として、娘さんと共に公証役場へ向かいました。代理人とはいえ、やはり少し緊張しましたが、公証人の先生の進行のもと、手続きは滞りなく進み、無事に離婚公正証書が完成しました。
手続きを終えた娘さんの表情は、どこか吹っ切れたような、すがすがしいものでした。「これで、前を向いて進めます」という言葉が印象的でした。離婚という一つの区切りをつけ、息子さんとの新しい未来に向けて、力強い一歩を踏み出された瞬間でした。
まとめ:離婚時の取り決めは公正証書が安心。行政書士にご相談ください。
離婚協議書を公正証書にする最大のメリットは、養育費などの金銭的な約束に対する強制執行力です。口約束や当事者間だけの書面では、いざという時に法的な手続きが煩雑になりがちです。
また、「相手と顔を合わせたくない」という場合でも、代理人制度を利用すれば、精神的な負担を軽減しながら手続きを進めることが可能です。
私たち行政書士は、
- ご夫婦の状況に合わせた離婚協議書・公正証書の案文作成
- 公証役場との連携、必要書類の準備
- 代理人としての公正証書作成手続きの代行
など、離婚に関する様々な手続きをサポートいたします。
離婚についてお悩みの方、公正証書の作成を検討されている方は、ぜひ一度、専門家である行政書士にご相談ください。あなたの新しい一歩を、全力でサポートさせていただきます。
東京都台東区で「お困りごとを解決する」行政書士をしております。
遺言・相続・医療法人設立・建設業許可・会社設立などのご相談を承っております!

