お役立ちコラム
10.272023
会社設立の全手順|基本事項決定から登記申請までの流れと注意点
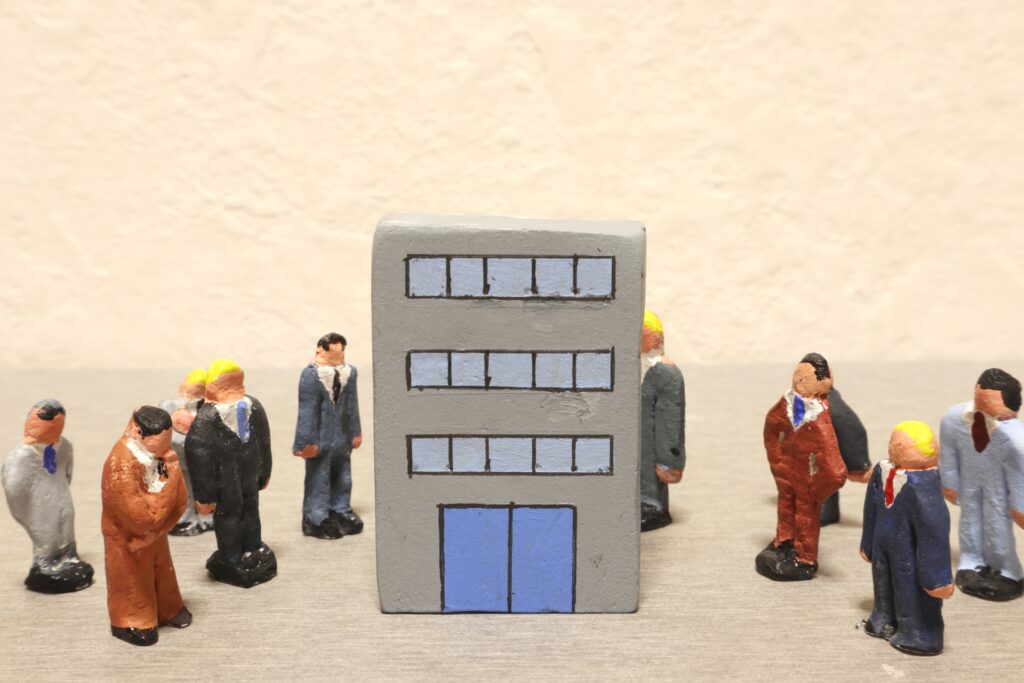
会社を設立したいけれど、何から手をつけていいか分からない…。「会社設立」と検索しても情報が多くて混乱してしまう、という方は多いのではないでしょうか?
確かに、会社設立には様々な手続きや決めるべきことがあり、複雑に感じるかもしれません。しかし、手順を一つずつ理解していけば、決して難しいものではありません。
この記事では、会社設立の基本的な流れ(手順)を、「①基本事項の決定 → ②定款作成・認証 → ③資本金の払い込み → ④登記申請」のステップに分け、それぞれのポイントや注意点を行政書士が分かりやすく解説します。
特に、後々トラブルになりやすい「事業目的」と「許認可」の関係についても詳しく触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 会社設立の第一歩:会社の形態を決める
まず最初に、設立する会社の形態を決めます。現在、新たに設立される会社の多くは**「株式会社」か「合同会社」**です。
- 合同会社 (LLC): 設立費用が比較的安く、経営の自由度が高いのが特徴です。有名な企業では、アマゾンジャパンやグーグルなどがこの形態をとっています。個人事業主から法人成りする場合や、コストを抑えたい場合に選ばれることが多いです。
- 株式会社 (KK): 社会的な信用度が高く、株式発行による資金調達がしやすいのが特徴です。将来的に上場を目指す場合や、外部からの出資を受けたい場合、あるいは取引先からの信用を重視する場合は、株式会社が適しています。
どちらの形態を選ぶかは、事業規模、将来の展望(上場、資金調達)、設立・運営コストなどを総合的に考慮して判断しましょう。迷った場合は、専門家である行政書士に相談するのも良いでしょう。
2. 会社設立の基本事項:事前に決めるべき6つのこと
会社の形態が決まったら、以下の基本的な事項を決定します。これらは定款にも記載する重要な項目です。
- 会社名(商号):
- 会社の顔となる名前です。使える文字や記号にはルールがあります(例: 株式会社を名前の前か後ろにつける)。
- 同一住所での同一商号は登記できません。類似商号にも注意し、事前に法務局のオンラインシステム等で調査すると良いでしょう。
- 本店所在地:
- 会社の「住所」です。自宅、賃貸オフィス、バーチャルオフィスなどが考えられます。
- 定款には最小行政区画(例:「東京都台東区」)までの記載でも可能ですが、登記申請までには具体的な地番まで決定する必要があります。
- 事業目的:
- その会社が「何をする会社なのか」を示すものです。現在行う事業だけでなく、将来的に展開したい事業も記載しておきましょう。
- 【重要ポイント】許認可が必要な事業を行う場合は、その旨を正確に記載しないと許認可が取得できない可能性があります。(後述)
- 資本金:
- 会社設立時の元手となる資金です。法律上は1円から設立可能ですが、会社の信用度に関わるため、一般的には数十万〜数百万円程度(運転資金3ヶ月分程度が目安)を用意することが多いです。
- 事業年度:
- 会社の会計期間(決算期)をいつにするか決めます。通常は1年間です。自由に決められますが、繁忙期を避ける、税理士と相談するなどの考慮が必要です。
- 出資者(発起人)と役員:
- 誰が会社にお金を出すのか(出資者=株主)、誰が会社の経営を行うのか(役員=取締役など)を決めます。株式会社の場合、出資者と役員は同一人物でも構いません。
これらの基本事項の決定には、調査や関係者との調整も必要になるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。一般的に、会社設立までには2~3週間程度かかります。
3. 会社のルールブック:定款の作成と認証
基本事項が決まったら、会社の最も重要なルールブックである**「定款(ていかん)」**を作成します。定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、会社の組織や運営に関する根本規則を定めた書類です。
定款に記載する主な事項
定款には、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)、記載しないとその効力が認められない事項(相対的記載事項)、それ以外の任意で記載できる事項(任意的記載事項)があります。
- 絶対的記載事項(記載がないと定款が無効になる):
- 商号(会社名)
- 目的(事業内容)
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(資本金の額)
- 発起人の氏名(名称)及び住所
- 発行可能株式総数(株式会社の場合)
- 相対的記載事項(定款に定めなければ効力がない):
- 株式の譲渡制限に関する規定(非公開会社とする場合)
- 株主総会以外の機関(取締役会、監査役など)の設置
- 役員の任期(原則2年、非公開会社は最長10年まで伸長可能)
- 現物出資に関する事項
- 株主総会の招集通知期間の短縮 など
- 任意的記載事項(上記以外で、法律に反しない範囲で自由に記載可能):
- 事業年度(決算期)
- 役員の員数
- 株主総会の議長 など
定款作成は会社運営の基礎となるため、慎重に行う必要があります。
定款の認証(株式会社の場合)
株式会社の場合、作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。(合同会社の場合は認証不要)認証とは、正当な手続きによって定款が作成されたことを公証人が証明する手続きです。一度認証を受けると、原則として自由に変更はできません。
【コスト削減!】電子定款の活用
定款は紙で作成することも、PDFファイルによる電子定款で作成することも可能です。
- 紙定款: 収入印紙代 4万円 が必要
- 電子定款: 収入印紙代 4万円 が 不要
電子定款を作成するには専用のソフトや機器が必要ですが、行政書士などの専門家に依頼すれば、この4万円を節約できます。会社設立の初期費用を抑えたい場合は、電子定款の活用がおすすめです。
定款作成は専門的な知識も必要となるため、不安な方は行政書士にご相談ください。
4. 会社の元手:資本金の払い込み
定款の準備と並行して、決定した資本金を払い込む手続きを行います。
- 払込先: 会社はまだ設立されていないため、会社の銀行口座はありません。発起人(出資者)個人の銀行口座に、各発起人が出資する金額を振り込みます。
- 証明: 振り込みが完了したら、その口座の通帳のコピー(表紙、名義人ページ、振込記録ページ)を登記申請時の添付書類として使用します。
前述の通り、資本金は1円から設立可能ですが、設立直後の運転資金や会社の信用力を考慮すると、少なくとも100万円以上、あるいは設立後3ヶ月程度の運転資金を目安に準備することをおすすめします。
5. いよいよ会社誕生:登記申請
定款認証(株式会社の場合)と資本金の払い込みが完了したら、いよいよ法務局へ会社設立登記の申請を行います。登記申請書に、認証済み定款、発起人の決定書、役員の就任承諾書、印鑑証明書、資本金の払込証明書などを添付して提出します。
登記申請日が会社の設立日となります。登記が完了すれば、法的に会社が成立したことになります。
※登記申請手続きは司法書士の業務範囲となるため、行政書士は司法書士と連携してサポートを行います。
6. 会社設立にかかる費用まとめ
会社設立には、主に以下の法定費用(実費)がかかります。
| 費用項目 | 株式会社(電子定款の場合) | 株式会社(紙定款の場合) | 合同会社(電子定款の場合) |
合同会社(紙定款の場合)
|
| 収入印紙代 | 0円 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 |
| 定款認証手数料 | 約50,000円 | 約50,000円 | なし | なし |
| 定款謄本手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 | なし | なし |
| 登録免許税 | 150,000円~ ※1 | 150,000円~ ※1 | 60,000円~ ※2 | 60,000円~ ※2 |
| 法定費用合計 | 約202,000円~ | 約242,000円~ | 60,000円~ | 100,000円~ |
※1: 資本金の額 × 0.7%(最低15万円) ※2: 資本金の額 × 0.7%(最低6万円)
上記費用に加えて、資本金、および行政書士・司法書士などの専門家への報酬が必要となります。
電子定款を利用することで、株式会社・合同会社ともに印紙代4万円を節約できることが分かります。
7. 【重要】会社設立で失敗しないための注意点
最後に、会社設立時に特に注意すべきポイントを2つ解説します。
①株式譲渡制限はつける?(公開会社 vs 非公開会社)
株式会社を設立する際、「株式の譲渡制限」を設けるかどうかを決める必要があります。
- 非公開会社(株式譲渡制限会社):
- 株式を譲渡(売却など)する際に、会社の承認(通常は株主総会や取締役会)が必要です。
- 意図しない人物が株主になるのを防ぎ、経営権の安定につながります。
- 役員の任期を最長10年まで伸長できます。
- 取締役会の設置が任意です。
- 中小企業の多くはこちらを選択します。
- 公開会社:
- 株式を原則として自由に譲渡できます。
- 上場を目指す会社はこちらを選択しますが、設立時から公開会社にするケースは稀です。
- 取締役会の設置が必須です。
特別な理由がない限り、設立時は非公開会社(株式譲渡制限を設ける)としておくのが一般的です。これにより、経営の安定性を確保しやすくなります。
②将来も見据えた「事業目的」と「許認可」の深い関係
定款に記載する「事業目的」は、非常に重要です。なぜなら、許認可が必要な事業を行う場合、定款の目的にその事業内容が正確に記載されていないと、許認可が取得できないケースがあるからです。
例えば、以下のような事業を行うには、許認可が必要です。
- 建設業許可
- 宅地建物取引業免許
- 古物商許可
- 飲食店営業許可
- 一般貨物自動車運送事業許可(運送業)
- 旅行業登録 など
「将来的に始めたい」と考えている事業でも、許認可が必要なのであれば、設立時の定款に目的として入れておくべきです。
もし、後から事業目的を追加する必要が出た場合、株主総会での決議を経て定款変更を行い、さらに変更登記の手続きが必要になります。これには、登録免許税(通常3万円)や専門家への報酬といった余計な費用と手間がかかってしまいます。
どのような事業目的を記載すればスムーズに許認可が取得できるかは、許認可の種類によって異なります。
許認可申請を見据えた会社設立をお考えなら、ぜひ許認可業務に詳しい行政書士にご相談ください。 設立段階から適切な事業目的を設定することで、将来の無駄なコストと時間を削減できます。
まとめ:スムーズな会社設立のために
会社設立の手順と注意点について解説しました。
- 会社の形態(株式会社 or 合同会社)を決める
- 基本事項(商号、所在地、目的、資本金など)を決める
- 定款を作成し、認証を受ける(株式会社)
- 資本金を払い込む
- 法務局へ登記申請する
特に、電子定款の活用によるコスト削減や、許認可を見据えた事業目的の設定は重要なポイントです。
会社設立は、ご自身で行うことも可能ですが、時間と手間がかかり、書類作成に不備があると修正が必要になることもあります。
当事務所では、電子定款作成によるコスト削減はもちろん、建設業許可、宅建業免許、運送業許可など、各種許認可申請を考慮に入れた会社設立サポートを得意としております。
会社設立に関するご相談、お手続きの代行は、ぜひ当事務所にお気軽にお問い合わせください。スムーズなスタートアップを全力で支援いたします。
東京都台東区で「お困りごとを解決する」行政書士をしております。
遺言・相続・医療法人設立・建設業許可・会社設立などのご相談を承っております!



